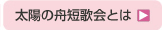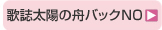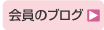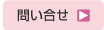十月一日は日本酒の日である。この日になると必ず思い出す歌がある。若山牧水の「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり」である。牧水は一日一升飲んだという。唐の李白も大の酒好きで「酒一斗詩百篇」と言われ、「山中にて幽人と対す」とする「両人対酌山花開 一杯一杯復一杯 我醉欲眠旦去 明朝有意抱琴来」など酒豪家李白の面目躍如。また「花間壺酒 独酌無相親 挙杯迎名月 対影成三人」(月下独酌)など牧水の世界に酷似する。我歌えば徘徊し、我舞えば影零乱す。
古来酒を詠んだ歌人は多い。然し昭和三年九月十七日、四十三歳で亡くなるまで約三百首の酒の短歌を作った牧水の右に出る者は多くはいまい。
酒のためわれ若うして死にもせば 友よいかにかあはれならまし
鉄瓶のふちに枕しねむたげに 徳利かたむくいざわれも寝む
妻が眼を盗みて飲める酒なれば 惶てて飲み噎せ鼻ゆこぼしつ
大正十三年の九州旅行で「とにかく思い残すことなく飲んで来た。揮毫しながら、大きな器を傾けつつ飲んだ。また、別に宴会なるものがあった。一日平均二升五合に見積もり、一人して約一石三斗を飲んできた、と数字に示されたときは、流石の私も、ものが言えなかった」とは以って瞑すべし、というべきか。 (松岡)
明治三五年九月十四日朝、正岡子規はガラス障子の外に夏の終わりゆく中庭を眺めながら、高浜虚子に口述筆記させる。「・・・たまに露でも落ちたかと思ふやうに、糸瓜の葉が枚枚だけひらひら動く。其度に秋の涼しさは膚に沁み込む様に思ふて何ともいへぬよい心持であった。何だか苦痛極って暫く病気を感じないやうなのも不思議に思はれた・・」そして、五日後の九月十九日午前一時、三十六才の若さで死去する。
正岡子規は、発句から俳句、和歌から短歌への革新を短い生涯のうちで成し遂げた。子規が短歌の革新に取り組んだのはカリエスが悪化し、殆ど寝たきりの生活を強いられた時期。病身を鼓舞して新聞「日本」に『歌詠みに与える書』を発表した。
何事にもすべて実証的であった子規が俳句においても短歌においても革新したのは「写生」である。死の床にあっても、夏の終わりの中庭を、虚子に口述筆記の写生をさせる。「糸瓜の葉が一枚二枚だけひらひら動く」。骨の髄まで写生精神に貫かれていたのである。尺ばかりの薔薇の芽に触れて見たくて花壇に向かう、さすれば、針やはらかに春雨が降っていたのである。
斎藤茂吉は「写生トイフコトハ、生ヲ写スコトデアル、生ハ即チいのちノ義デアル」として「實相に観入して自然・自己元の生を写す。」これが短歌の写生であると言う。
子規と茂吉の詩精神の原点を今度考えたい。 (松岡)
「悪魔退くる力なきものの行為の半は其身もまた悪魔なれば也。已に業に其身悪魔の行為なりて悪魔を退けんは難し」一九一三年八月一日、足尾鉱毒との闘いに命をかけた田中正造は日記に記し、翌日に倒れた。再び立てず九月四日に逝く。菅笠と合切袋一つをのこした。中には帝国憲法とマタイ伝を綴じたもの、渡良瀬川の石があった。
田中正造は三宅雄二郎宛書簡(明治三七年一一月二六日)のなかで「戦争の罪悪は論を要せず」として「戦争は必要なりとする事ありとするも、我国の内政の如き、公盗横行の政府にして妄りに忠直の人民を殺すことを敢えてするものの戦争を奨励するに至りて言語道断なり」と述べている。戦争は罪悪であり世界の軍備は全廃すべきである(正造翁談)とした思想は、「戦争は正義」とされた時代にあってまことに偉大であった、と言わざるを得ない。その田中正造に狂歌集がある。そのいくつかである。
人ハ皆桜のころになりにけりうかれあつまる人の花山
各々が我田に引ける水ほどのすめる心を持つ人ぞなき
よの人のあわれをおもふ真心の尚つれなきぞ秋の夕ぐれ
天が下見れバ社会は面白し山田かかしも雪のだるまも
足尾鉱毒事件に私財を擲って闘い信玄袋ひとつ遺して逝った田中正造に、世の中は面白い、山田のかかしも雪だるまも、と詠んだ狂歌があった。歌詠みは柔らかな心と同時に社会に対する厳しい判の目を持たねばなるまい。 (松岡)
ある日の暮方の事である。人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。よく知られている『羅生門』の書き出しである。
芥川龍之介は自ら装丁した第一短編集『羅生門』の扉に「君看ヨ双眼ノ色語ラザレバ愁ヒ無キニ似タリ」と入れた。白隠禅師の「君看双眼色不語似無憂」(さあ、その目の色をご覧なさい。何も言わなければ憂いがないように見えるでしょう)である。この時から十年、芥川の愁いは彼の生命を削りとった。彼の憂いとは何であったか。言葉である。
辞書のなかの言葉は死語である、文の中に定まる姿で屹立したとき初めて生きる、とした芥川は、自分のスタイルすなわち言葉を発見し組み立てるのに命を削った。
「青蛙おのれもペンキぬりたてか」という俳句など短詩型文芸にも鋭い。江口喚によれば、友人たちに書き送った書簡の端に書かれた俳句や短歌はそれぞれゆうに一冊の本になるという。短歌には真剣に打ち込み「朝顔のひとつはさける竹のうらともしきものは命なるかな」「春雨はふりやまなくに浜芝の雫ぞ見ゆるねてはおれども」などすぐれ「わが門のうすくらがりに人のゐてあくびせるにも驚く我は」(病中愚作)は自殺直前の心理を鋭く表現している。
一九二七年七月二十四日未明、『続西方の人』を脱稿し枕元に聖書と遺書をおいて永遠の眠りについた。外は雨が降りしきっていた。 (松岡)
明治四十四年(一九一一)六月一日、青鞜社発起人会が開催された。その三ヶ月後『青鞜』が創刊される。「原始、女性は実に太陽であった。真正の人であった」というよく知られた言葉は、二十六歳の平塚らいてうによって書かれた。創刊に与謝野晶子は「山の動く日来る かく云えども 人はわれを信ぜじ」の詩を寄せる。
明治女歌の夜明けを告げたのは、与謝野晶子である。『みだれ髪』で「やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君」と詠って熱狂的な支持を受け「やは肌の晶子」と呼ばれる。また「乳ぶさおさへ神秘のとばりそとけりぬここなる花の紅ぞ濃き」と性愛の扉を押して官能の歓喜を大胆に歌い上げ、浪漫派歌人のスタイルを確立した。
然し晶子は優れた女流浪漫派歌人であっただけではない。召集され旅順攻囲戦に加わった弟を嘆き『君死にたまふ事なかれ』を発表。大町桂月に「家が大事也、妻が大事也、國は亡びてもよし、商人は戦ふべき義務なしといふは、余りにも大胆すぎる言葉」と批判され、「たいさう危険なる思想と仰せられ候へど、当節のやうに死ねよ死ねよと申し候こと、また何事にも忠君愛国の文字や、畏おほき教育勅語などを引きて論ずることの流行は、却って危険」と反論し、「歌はまことの心を歌うもの」と一蹴する。
山動く日の来たことを与謝野晶子は心底認識していた人間であったことを歌人は知らねばならない。 (松岡)
長谷川等伯没後四〇〇年特別展が上野の国立博物館で開催された。国宝三件、重文約三〇件を一挙公開という触れ込みに、長蛇の列、その人垣を縫って覧てきた。
等伯は能登に生まれ、養祖父、義父に繪の手ほどきをうけ、信春と名乗り、繪仏師となる。三十三歳のころ上洛し、狩野派一門の牙城に迫り五一歳にして千利休の後押しもあり大徳寺三門の金毛閣の天井画を描く。五十二歳で永徳と御所の障壁画を争い、のちに祥雲寺の障壁画を制作。六十一歳のとき一族への祈りをこめ、よき理解者であった日通上人に「大涅槃図」を寄進する。波乱万丈の生涯だった。
国宝「楓図壁貼付」を始め重文「三十番神図」「日堯上人図」「利休図」など心惹かれる繪に多く逢ったが、溜息が出たのは「松林図屏風」であった。濃き薄き松の朧が近く遠く心を捉える。手前の濃い松の木の松葉が以外に力強く、と言うより乱暴とも言えるタッチなのに驚かされた。ふるさと能登七尾の海岸の松を描いたものという。
朧に濃き薄き松が洵に強く浮き出してくるのをじっと覧ているうち、その余白の大きさが迫ってきた。この空白は一体何だろう。不意を突かれた。このしろい空白。何も語らずに凡てを語る。そういえば松尾芭蕉も「謂応せて何か有」といっていた。表現の奥底はすべてを「いいおおせない」ことである。余情匂いは表現過剰からは生じないことを改めて識らされた「松林図屏風」だった。 (松岡)
西洋の詩人T・Sエリオットは四月は残酷な季節と詩ったが、日本ではやはり桜さくらである。まさおなる空よりしだれざくらかな、という富安風生の伏姫桜を詠んだ句碑が市川の弘法寺の境内にある。まこと見事な桜である。
桜といえば、やはり、西行の、ねがはくは花の下にて春しなんそのきさらぎの望月の頃ころ、である。花とは勿論桜。
兵衛尉佐藤義清は、保延年(一一四〇)二十四歳の若さで有望な官途を捨て、出家して「西行」と名乗った。西行の出家の動機を、川田順(『西行』)は厭世説、恋愛原因説、政治原因説、とその総合原因説をあげているが、藤岡作太郎の「西行にとりては和歌は遊戯文学にあらず、擅ほしいままに山川花月に対して、おのが感情を述べんとするにあり」(『異本山家集』として天性の詩人は詠歌を余技とする官人に飽きたらず遁世の道を選んだとする説を採りたい。
世を厭いもし恋に破れたことも政治に無常を覚えたこともあろう。しかし、畢竟、西行は和歌に出家したのである。詩歌に出家したのである。西行にとり桜の花は和歌であり詩歌の象徴であった。詩歌の下で死ぬことを願ったのである。
歌人はすべからく詩歌に出家しなければならない。日常生活から出家して詩歌の世界に入りまた其処をでて現実世界に戻る。そしてまた詩歌の世界に没入しまた戻る。その往還こそ歌人の生きる道であると愚考する。 (松岡)
月日は百代の過客にして行きかふ年も又旅人也。舟の上に生涯を浮かべ、馬の口をとらえて老をむかふる者は日々旅にして旅を栖とす。と歳月も生涯も旅と観じた松尾芭蕉は、古人も多く旅に死せるありとして、元禄二年弥生三月も末の日奥羽長途の行脚「奥の細道」の旅に出立します。
芭蕉は漂泊の詩人と云われます。旅の詩人です。旅の中に自己の新しい俳諧すなわち文学を発見していったのです。尾形によれば、「野ざらし紀行」「鹿島詣」「笈の小文」「更科紀行」は俳壇の低迷を打破し、漢詩文調以後の新しい俳風を開発するための芸術的営為にほかならなかったわけであり「崩壊した都市俳壇にかわって台頭してきた地方俳壇を歴訪することによって、新風の伴侶としての新しい連衆との出会いを求め、またひとつには、各地の歌枕を巡礼することによって、古人の詩心の伝統を探り、そこに新しい創造への源泉を汲もうとした」のです。「奥の細道」の旅で〝かるみ〟の志向と〝不易流行〟の理念を発見したといえます。
与謝野晶子は、鉄幹が常に新しい歌を詠んでいったと言っています。歌詠む者は、言い換えれば文学を志すものは、いや、あらゆる分野において、新しきを求め自己改革することにこそ創作の意味がある事を認識したい。 (松岡)
昭和六十三年一月の創刊号(通巻五十六号)から編集人を引き受け、二月号より、巻頭言を担当した。以来、ある一時期と、ナイルを融合した一年七ヶ月を除いてほぼ平成の時代を書き継いで来た。平成ももう二十二年を数える。思えば長い年月だった。一番下の娘はその時四歳、もう二十六歳になる。私の娘が成長したように、果して太陽の舟短歌会は成長したのであろうか。あまりに身近すぎて私と、あるいはもう身体の一部になっていて、私にはその成長が分からぬらしい。
阿部先生は何を書いても何一つ批評批評らしい事はおっしゃらなかった。時折、冗談めかしく「君の巻頭言は格調高いね」とおっしゃる。それが何よりの力であり恐怖だった。しかしそうおっしゃって下さる先生を失なってはや九年、無我夢中の毎月だった。今思い返しても何も浮かんで来ず、目の前に毎月の雑誌が積まれているだけ。幸いに六年前に松岡さんが編集を引き受けて下さった。大きな荷物をつ下す事が出来た。私が巻頭言を続けて来れたのも、松岡さんが編集を引き受けて下さったから。
そして来月から、この頭言を松岡編集長が受け持って下さる事と成った。なぜもっと早くに引き渡さなかったのだろうと、自分の迂闊さに愕然とする。松岡編集長は、私などより遥かに学識も高く人生経験も豊かな方。これから太陽の舟短歌会が進む方向に巨大な燈台となって豊かな灯かりを灯し、私達を導いてくれるに違いない。私は今からそれが楽しみでわくわくしている。最後に長い間私の頭言を読んで下さった会員の皆様に衷心よりお礼申し上げて筆を置く事とする。 (髙﨑)
初春を言祝ぎ、一年の御多幸を心より祈念申し上げます。
「日本感性工学会」という学会をご存知だろうか。平成十年創立のまだ若い学会だが、急速に会員が増えているという。その中に「感性哲学部会」という部会がある。その位置付けは「衣・食・住から環境・生命・情報にいたる感性のかかわる領域での、人間と社会のビジョンを作るコンセプト・ワーク」だ。感性とは外界からの感覚情報を受容し、経験に伴う刺激に反応するもの。また、感受性や情意欲求、感情、情緒などを含む心の能力。しかし、感性は心に深く感じる能力であるとともに「するどい感性」や「豊かな感性」などと、単に受動的なものではなく、むしろ創造性をもった能動的な能力と考える。したがって、感性工学の研究においては「センス(感性)は情報量に比例する」と定義する。
私達は短歌を批評する時に、その感性は作者天与のものと表現しがちであるが、感性は決して天与のものでは無く、作者の日々の努力の賜であると改めて知らされる。したがって、私達は努力する事によって、豊かな情報量(学問・知識)を獲得し、感性が研かれその結果として良い歌を創作する事が出来る。
江戸時代初期の読み物作者・寒河正観は、その著「子孫鑑」の中で、「下手は上手の下地なり。下手よりだんだん上手になるなり」と述べている。私は自分が決して感性の豊かな人間ではないと思っていたが、今年は一念発起、感性を研いて良い歌を作ろうと思う。(髙﨑)
「三百号記念号に寄せて」
雑誌「太陽の舟」がとうとう三百号の記念号を出すに到った。昭和五十二年十月、伊那谷で阿部先生の第一歌碑除幕式のあった夜、岸田君が歌誌発行の思いを熱く語った。その当時私は短歌より熱い思いを抱くものがあったのでその参加に加わる事は無かった。しかし昭和五十三年十月、第三号で支部発足が図られ、私も一支部に名を連ねる事となった。初めて歌を出したのは、昭和五十三年十二月の父の死で悲しむ私に阿部先生はやさしく作歌を勧めて下さったからである。それが始まりだった。以来雑誌「太陽の舟」は長い創刊準備の時を持つに到る。それは十年、五十五冊に及ぶ。この長さはある意味短歌結社を持つ事への阿部先生の逡巡の長さでもあったろう。先生は「これ程長く、これ程多くの創刊準備号を出した結社は空前にして絶後だ」とよくおっしゃった。そして、昭和六十三年一月一日、満を持して創刊号として第五十六号は発行された。阿部先生の「創刊宣言」を全文掲載する。私達の太陽の舟短歌会の新たなる出発の宣言であるからだ。これからも決して変わる事の無い太陽の舟の支柱である。
「創立宣言」夜の舟から昼の舟へ 阿部 正路
今、私たちは、高々と帆をあげて出発する。さらば、創刊準備号。
太陽の舟短歌会を結んだのは、昭和五十二年の秋。そして、最初の創刊準備号が発行されたのは、昭和五十三年の六月。以来、確実に隔月刊を守って十年、五十五冊を重ねて創刊への基礎を固めた。
私たちは、長い間、胎内に在った。そして今、私たちは、新しく生まれた。折から、エジプトのクフ王の大ピラミッドの西端で〈太陽の舟〉が発見された。ピラミッドの南面の東端で全長約四十メートルの太陽の舟が発見されたのは一九五四年。かくして、対をなす二隻の太陽の舟が確認されている。
太陽の舟は、太陽神を運ぶ。東から西へ。日の出から日没まで空をゆく〈昼の舟〉。そして、地下の世界を西から東へ移動する〈夜の舟〉。二つの舟は一つになって無限循環の世界をとどまる事なく行く。今私たちは蘇生し、昼の舟を漕ぐ。力をこめて、悠久の世界に立ち向かい、決して屈しないと誓う。
こうして私達太陽の舟は悠久の世界に立ち向かいながらついに三百号の発行に到った。多くの先駆者達を失なった。青翔短歌会と融合し、雑誌「ナイル」を発行、再び分かれて「太陽の舟」に戻った歴史をも持つ。人の一生と同様に太陽の舟も多くの紆余曲折があった。そして今がある。その事を何よりも大切に、私達は悠久の世界に立ち向かい、決して屈しない。何よりも真に感動にあたいする歌を作るために。(髙﨑)
台風の影響で外は激しい雨。私は何をするとも無く外を眺めながら、ふと若い頃に歩いた奈良の芋峠の野仏や夏に行った鋸山の磨崖仏を思った。あの仏達は今激しい雨の中に身を晒しながら、ひっそりと佇んで居るのであろう。人知れず何百年の歴史を刻みながら、風雨や炎天を佇み続ける野仏や磨崖仏に私は言い知れぬいとおしさを感じた。西村公朝は「祈りの造形」日本放送出版協会)の中で、「私にとりましては、この道端で苔むしている石仏こそ、まさに如の世界観をあらわしているといえるのです。お堂にまつられている仏像よりも、この方がはるかに大きなスケールです。周囲の景色そのものが仏殿なのですから。そして、石仏の前にある雑草や花こそ、自然の供物といえましょう。」と述べている。
私はこの文章に強く心引かれる。人々に珍重され崇められる仏像よりも、天然自然の中で自在に姿を変化させながら佇み続ける仏像こそ私は美しいと思う。阿部先生は私の最初の歌集「能登」の扉の写真に大切にしていらっしゃった野仏の拓本をくださった。そのお心は正にこの西村公朝の文章に凝縮されているのではあるまいか。そしてそれはそのまま歌人としての心構えを私にくださったのだと、今にしてしみじみ思う。
阿部先生は、繰り返しおっしゃった。「歌人に素人も玄人もない。真に大切なのは、どれ程良い歌を作ったか。真に感動にあたいする歌を作ったか。それが歌人の全てなのだ。」と。それは私に野仏の様な歌人になれと先生が暗に諭されたことなのであった。 (髙﨑)
富士正晴の「わが書斎兼客室兼寝室の前に、半坪ばかりの細長い池がある。」で始まる「蛙の声」と言う文章に「数年前、ラジオの録音にきた放送局の人が蛙の多さと、蛙の声にあきれた。これから蛙の声がいる時はここへ来ればいいわけですねえといった。いっただけで取りには来ないが、そういいたいほど、夏蛙の鳴声は猛烈である。」とある。四十年前の大阪府茨木市の自宅での事。ちなみにこの文章は「三島由紀夫が蛙の声を聞いてあれは何の声かとたずねた話は何かあわれである。」で終わる。
四年後の鴨川の私の住む家の周囲で田植が始まる四月頃からこの猛烈な蛙の声は終夜止む事は無い。しかし稲刈りが終るの末にはぴたりと止む。いったいあの沢山の蛙はどこへ行ってしまったのか。土に潜って冬眠してしまったのだろうか。代って斉に虫が鳴き出す。今までどこに居たのかと思う程に色々な虫の音がかまびすしい。そして見上げると空は深く澄んで、も星も輝きを増している。日中の暑さにげんなりして夏を引き摺っている人間を尻目に季節は瞬時に見事な引き継ぎを終えてしまった。
田舎暮しを始めて三年目、まだまだ地球は豊かな星である事を実感する。この豊かな星を私達は次世代に残して行くべき責任を持つ。地球温暖化を食い止める為、先進国と言われる国に住む私達は、真剣に便利である事について考える必要があるのではあるまいか。全ては便利を求める人間の欲望から生じた科学や文明の進歩がもたらしたものであるからだ。そしてその欲望は人の心までも破壊している。九月九月の初め、銀座を歩きながら高層ビルの谷間で私は悪寒を禁じ得なかった。 (髙﨑)
歴史は繰り返すというが、現在の自民党と民主党のマニフェストによるバラマキ戦争を「昭和初期の保守二大政党のバラマキ戦争のようだ」と言う人がいる。
この二大政党の政権欲が国民の信頼を失い軍部の台頭に繋がり、結果としてあの未曾有の戦争があった。
四年前、否小泉の登場からマスコミを含めて国民総白痴の感を強くしたが、今回も目に見えぬ「風」探しに国民総白痴状態になっていまいか。北朝鮮の核の脅威を利用して、首相その他に日本も核武装を辞せずと言わしめている醒めた人々の存在を隠すように。
阿部先生は短歌を詠む心構えの一つとして「目に見えぬものを見よ」と仰しゃった。
路傍の小さな花を美しいと思う。その美しさの本質はどこにあるのか。付近の様子、花の枝葉、空の色、風の色まで含めた美の中心に存在する花の美こそ、存在を越えた存在の美。私達歌人は無意識の内にそんな物の見方を身に付けて来た。
そしてそこから物事の本質を見、言葉を紡いで来た。短歌を始めてから物の見方が変わったとよく聞くのはこの事を自覚する言葉である。
私達は今本当に重大な岐路に立っている。信頼出来ぬ政治家に票を投じねばならぬ虚無を抱きつつ、それでもマスコミやある思惟的集団に惑わされる事なく自分の信念を完遂する事は容易ではない。
だからこそ歌人として培ったこの真実を、本質を見極める目を大切に今起きている物事を把握し行動しなければならない。その事が必ずや成熟した政治体制と国民本意の互助精神に満ちた国家を生むと私は信じている。