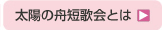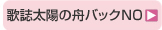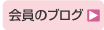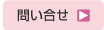巻頭言(Vol.32 No.5)2010.5.01
長谷川等伯没後四〇〇年特別展が上野の国立博物館で開催された。国宝三件、重文約三〇件を一挙公開という触れ込みに、長蛇の列、その人垣を縫って覧てきた。
等伯は能登に生まれ、養祖父、義父に繪の手ほどきをうけ、信春と名乗り、繪仏師となる。三十三歳のころ上洛し、狩野派一門の牙城に迫り五一歳にして千利休の後押しもあり大徳寺三門の金毛閣の天井画を描く。五十二歳で永徳と御所の障壁画を争い、のちに祥雲寺の障壁画を制作。六十一歳のとき一族への祈りをこめ、よき理解者であった日通上人に「大涅槃図」を寄進する。波乱万丈の生涯だった。
国宝「楓図壁貼付」を始め重文「三十番神図」「日堯上人図」「利休図」など心惹かれる繪に多く逢ったが、溜息が出たのは「松林図屏風」であった。濃き薄き松の朧が近く遠く心を捉える。手前の濃い松の木の松葉が以外に力強く、と言うより乱暴とも言えるタッチなのに驚かされた。ふるさと能登七尾の海岸の松を描いたものという。
朧に濃き薄き松が洵に強く浮き出してくるのをじっと覧ているうち、その余白の大きさが迫ってきた。この空白は一体何だろう。不意を突かれた。このしろい空白。何も語らずに凡てを語る。そういえば松尾芭蕉も「謂応せて何か有」といっていた。表現の奥底はすべてを「いいおおせない」ことである。余情匂いは表現過剰からは生じないことを改めて識らされた「松林図屏風」だった。 (松岡)
Copyright 2009 Taiyounofune tankakai All Rights Reserved.